沖縄のお盆は旧暦で行う家庭が多い!
沖縄のお盆の特徴と言えば、
旧暦の7月13日から15日までの期間です。
なので、毎年お盆と言うのは、
新暦に直すと日にちがズレますので、
今年のお盆はいつになるの?
なんて会話はしょっちゅう耳にします。
旧暦で行う理由としては、
お盆はご先祖を迎える日ですので、
新暦のことを知らないご先祖は、旧暦にしかこないので、
お盆は旧暦のまま行うというのが、一般的だと思います。
新暦の8月13日から15日にお盆としている家は、
ほとんど無いと言っても良いかもしれません。
ちなみに、
旧暦の7月13日を「ウンケー」と言い、
7月14日を「ナカヌヒー」と言い、
7月15日を「ウークイ」と言います。
沖縄ではお盆に遊びに行かない?
ご先祖を何よりも大事に沖縄ですので、
「お盆=遊びに行く」という感覚はあまりなく、
親戚一同が祖父母の家に集まって、
みんなで過ごすということが多いのです。
子供にとっては遊び感覚でしょうが、
大人にとっては色々と準備などもあって、
女性はある意味で、仕事感覚だと思います。(笑)
よくニュースで、
海外旅行に出かける人などが報道されますが、
沖縄人の感覚では、
お盆なのに仏壇に手を合わせないなんて、
しかも海外とかありえない!といった、
感覚を持っている人も多いと思います。
それに気をつけることと言えば、
海や川など、水辺では遊ばないということ。
もちろん、迷信だという人もいますが、
ヒロヒロは、そういう文化だと思って、
行かないようにしています。

お盆はお墓に行かない家庭も多い!
ちょっと意外かも知れませんが、
沖縄では、ご先祖が家に来てくれるから、
お墓には行かずに家で過ごす家庭も多いです。
お墓に行く家庭もありますが、
これは家庭によってかなりのバラつきがありますので、
お墓に行く家庭と、行かない家庭の基準というのは、
どこからどこまでなのか、あまりよく分かりません。
お盆にはエイサーが楽しみ!

今ではエイサーのいろいろなイベントがありますが、
元々はお盆の時期に行うのことが始まりで、
沖縄全体の行事ではなく、どちらかと言えば、
本島の中部地区で、盛んに行われているのです。
ヒロヒロの地元も中部地区でしたので、
小さい頃は、お盆が本当に楽しみでした。
ですが、今では太鼓の騒音問題とか、
深夜までの活動などが問題になっており、
ちょっと残念ではありますが、
時代にあった活動を続けていかないと、
そのうち縮小してしまうだろうと懸念されています。
お盆の〆は“ウチカビ”を燃やすこと!
ウチカビとは、あの世のお金です。↓

こんな感じで、スーパーに売っています。(笑)
お盆の最後の日の夜には、
ご先祖があの世に戻るので、
その前にお小遣いを渡すのです。
でも、この世の物を渡しても、
あの世まで持って行くことができず、
持って行くようにするためには、
燃やす必要があるとされていて、
お盆の最後の〆というのは、
ウチカビを仏壇の前(家の中)で燃やすのです。
見たら絶対にビックリしますよ!
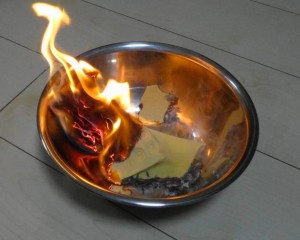
それに、このウチカビと言うのは、
本当によく燃えますので、
火の粉が舞って、畳を焦がしてしまうことは、
沖縄あるあるかも知れません。
おすすめ記事



最新情報をお届けします
Twitter で「沖縄が東京に住むと、」をフォローしよう!
Follow @okinawa101602


